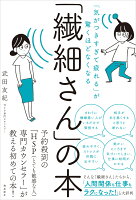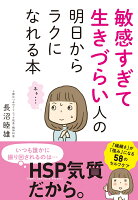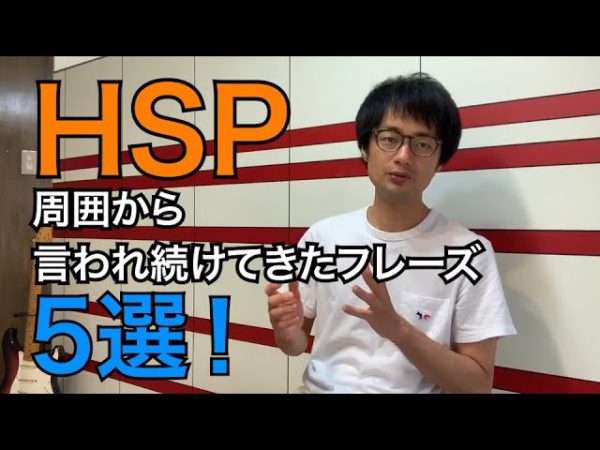【まとめ】HSPの特徴「とても敏感」の意味を提唱者の本に沿って解説!

HSPは「とても敏感」とか「刺激を受けやすい」と聞きましたが、どういう意味なのかよく分からないのですが…。
「目や耳が良い」とは違うのでしょうか?
それと「刺激」というのは、どういうものを指すのでしょうか?
今回は、そんな疑問について解説します!
ベースにするのは、エレイン・N・アーロン博士の著書(日本語訳版)「ささいなことにもすぐに『動揺』してしまうあなたへ。」(以下「本書」と言います)
アーロン博士はアメリカの心理学者であり、HSPの提唱者です。
※この記事のグレーで囲んだ箇所は、全て本書からの引用です。
HSPとは?

「HSP」とは「Highly Sensitive Person」の頭文字を取ったもので、本書では「とても敏感な人」と訳されています。
翻訳者は、「Sensitive(センシティブ)」ついてこう述べています。
「敏感」と訳しましたが、「繊細」とか「感受性の強い」「感じやすい」などの意味があります。
刺激に対して反応しやすいということだと考えてもらえればいいと思います(P3)
「敏感」や「繊細」という言葉は、人によってはマイナスイメージを持つと思います。
その点、「刺激に対して反応しやすい」という表現は中立的で分かりやすいです。
つまりHSPは、「とても刺激に対して反応しやすい人」なんですね。
HSPが反応してしまう「刺激」とは?

「刺激」と聞くと、音・光・匂い等をイメージします。
でもHSPが反応する刺激は、それだけではありません。
ふつう刺激とは外界から受けるものだと思われているが、カラダの内側から起こる場合(痛み、筋肉の緊張、飢え、渇き、性欲など)もあるし、記憶や空想、考えや計画などが引き起こすこともある(P51)
確かに僕は、痛みに敏感です。
指先の小さな切り傷でさえ、ジンジンと痛む感覚が続きます。
渇きにも敏感で、ペットボトルを持っていないと不安になります。
目薬とリップクリームも手放せません。
とても敏感とは?

聴覚や視覚、あるいは身体感覚が他の人より優れているということではない(事実、たくさんのHSPは眼鏡をかけている)。
この個人差は、外から受け取った情報をどれくらい丁寧に処理するかということにある(P48)
「とても敏感」というのは神経の肌理(きめ)が細かいということですが、これはたとえていうなら、目の細かい網のようなもの(P4)
つまり、
・HSP→目の「細かい」網を持った人
・非HSP→目の「荒い」網を持った人
目が細かい分、大小色んな刺激をキャッチしてしまうわけです。
そして、
普通の人にとっては「適度な刺激」が、HSPにとっては「かなりの刺激」になってしまう。
普通の人にとっての「かなりの刺激」は、HSPにとっては「耐え難い刺激」(P49)
普通の人が見逃してしまうような微妙なサインを自然に取り込んでしまうので、最適レベルの神経の高ぶりの域を超えてしまいやすい(P73)
だから非HSPにしてみれば、
・気にし過ぎじゃない?
・どうしてそんなに疲れるの?
と不思議なんですよね。
HSPと非HSPの「敏感さ」の違いとは?
これは僕の理解ですが、違いはこうです。
1.そもそも、受け取る(=網に引っ掛かる)刺激の量と質が違う
2.同じ刺激を受け取っても(=網に引っ掛かっても)、気になる量と程度が違う
3.同じ刺激を受け取っても(=網に引っ掛かっても)、考える時間と深さが違う
この一連の違いが、「敏感さ」の大きな違いだと思います。

例えばHSPと非HSPが同じカフェに入ったとします。
HSPは、
・隣の席との距離
・自分や他人の感情
・料理やドリンクの味
・室内の温度、空調の風
・お店やお客さんの雰囲気
・料理・香水・体臭・タバコなどの匂い
・他の人の会話の内容・話し方・声量、態度
こういった刺激を常に受け取り、色んなことが気になり、深く・時間を掛けて考えます。
ところが非HSPは、
・そもそも気付いてすらいない(受け取る刺激の量と質が違う)
・気付いても気にならないか、ちょっと気になる程度(気になる量と程度が違う)
・気になってもそれほど時間を掛けず、深く考えない(考える時間と深さが違う)
もちろんHSPにも非HSPにも個人差はあるので、あくまでもイメージです。
HSPは常に神経が高ぶってるの?

HSPは色んな刺激に反応し、神経が高ぶることが多いです。
ただ、
HSPはいつも神経が高ぶっているというわけではない。
日常生活や睡眠中において「慢性的に神経が高ぶっている」のではなく、新しい刺激や長引く刺激に対して神経が高ぶりやすいのである(P56)
僕の理解では、「新しい刺激」とは「未知の刺激」ではありません。
「異質の刺激」というイメージです。
例えば家にいる時は落ち着いていたのに、家を出て電車に乗ったら、大声で話す人がいたとします。
「大声」という刺激は決して「未知の刺激」ではありませんが(いつも悩まされていますよね。)、その時まで無かった「異質の刺激」ですよね。
たとえ「既知の刺激」であっても、刺激は刺激です。
HSPにも個人差はあるの?

HSPは、
「鈍感な人々」とはまったく性質の異なる独自のグループであるようだ。
そして、同じグループの中でも、敏感さの度合いはさまざまである。(中略)彼らは人生経験によって、または意識的な選択をして、より敏感になったり、そうでなくなったりすることがある。
つまりHSPは基本的にはひとつのグループだが、グループ内を細分化する境界線はそれほどはっきりしていない(P89)
非HSPは常に鈍感なの?

ここまで読むと、
・HSP=敏感
・非HSP=鈍感
というイメージを持つかもしれません。
しかし、そんな明確に分けられるものではありません。
ほとんどの人は、自分で認めようと認めまいと過敏な面を持っており、何かの拍子にその敏感さが顔を出す(P10)
HSPであれ非HSPであれ、良い意味での繊細さはみんな持っているもの(P11)
参考文献
なぜか書店・楽天・アマゾンで新品が無く、Amazonで2,000円を超える中古を買いました…。
買う時はちょっと悔しかったですが、本当にオススメの本です。
読み進めると、グッとくるものがあります。
YouTubeでも取り上げてます!
HSPの方にオススメの本!
実際読んだ本の中で、次の3冊がオススメです。
特に、
「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる 「繊細さん」の本
は凄く良かったです。
まとめ
HSPという概念の提唱者であるアーロン博士の著書をベースに、「とても敏感」とはどういう意味なのか?HSPが反応してしまう「刺激」とは一体何なのか?について解説しました!